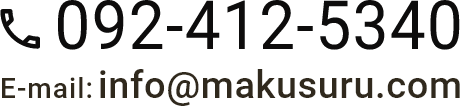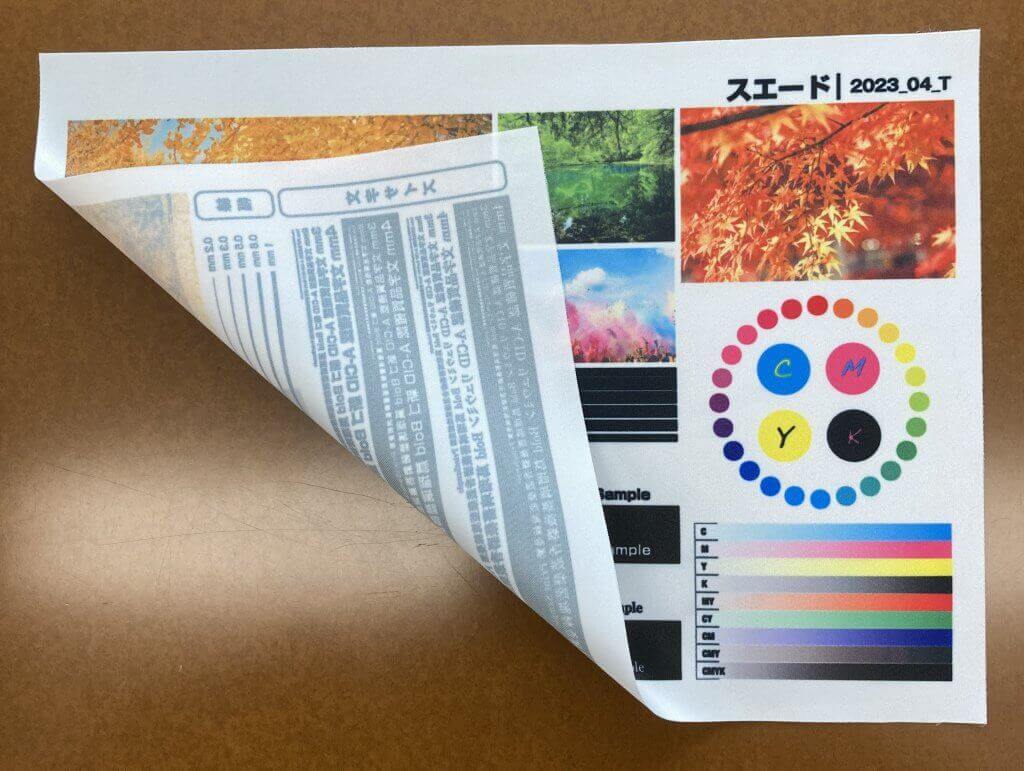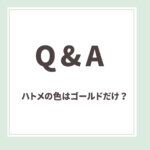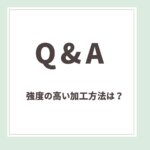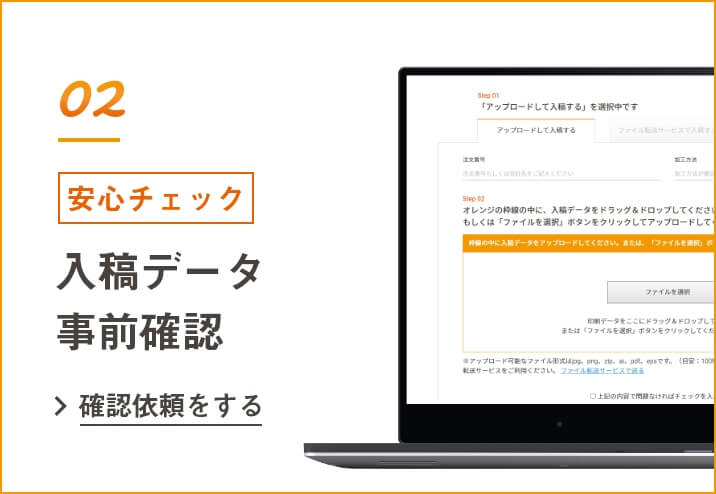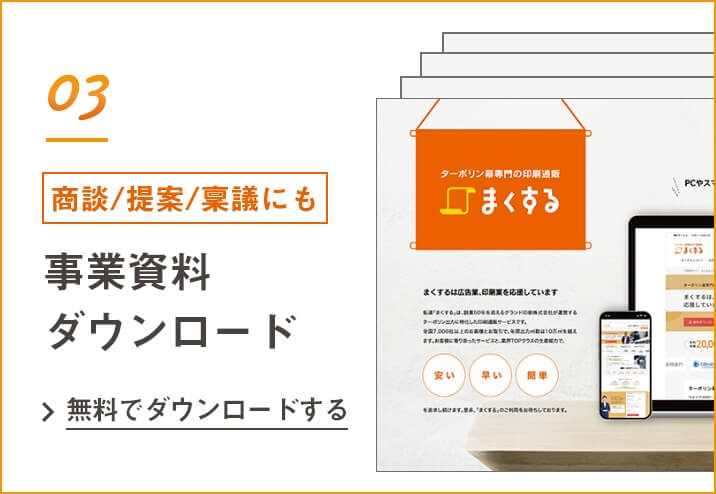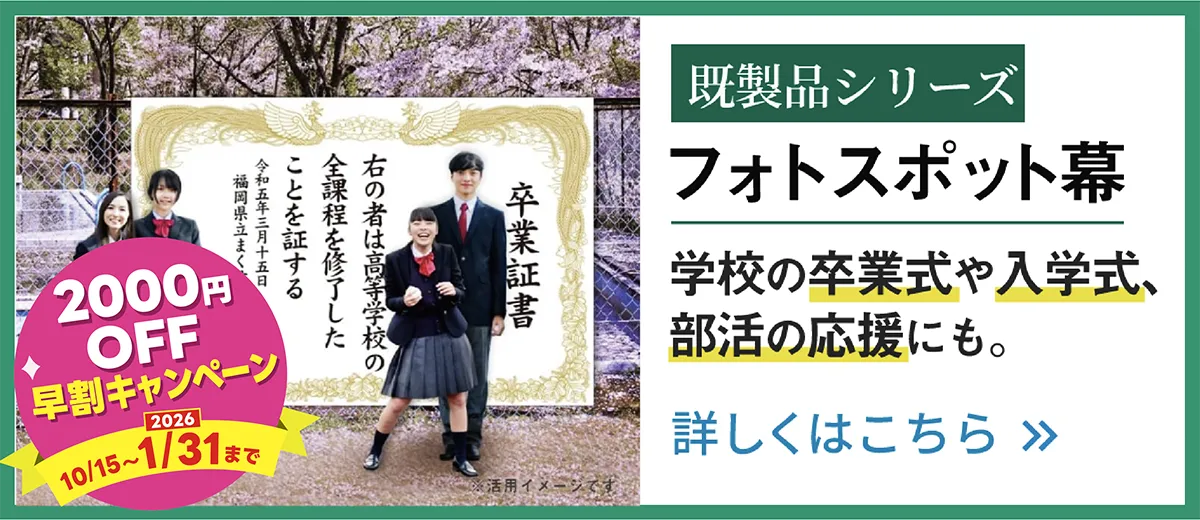歩道橋や道路に横断幕を設置したい方へ|許可・ルール・おすすめ素材を徹底解説
「歩道橋に横断幕を掲げて地域イベントをPRしたい」「道路沿いのフェンスに大会告知を出したい」──そう考えたことはありませんか?
街中では、「交通安全運動実施中」「〇〇大会開催」「地域清掃デー」などの横断幕をよく見かけます。しかし、いざ自分たちで掲出しようとすると、「どこに許可を取ればいい?」「道路に設置しても大丈夫?」と疑問に思う方が多いのではないでしょうか。
この記事では、歩道橋や道路沿いに横断幕を設置する際のルールや申請の流れ、安全な素材選びとデザインのコツをわかりやすく解説します。後半では、実際に歩道橋に設置された事例も紹介します。
目次
歩道橋や道路に横断幕を設置できる?
まず知っておきたいのは、どの場所にでも自由に横断幕を掲げられるわけではないという点です。道路や歩道橋は公共空間に分類されるため、道路法や屋外広告物法などの規制を受けます。これらの法律では「安全を損なう・景観を乱す・通行を妨げる」行為を制限しており、無断設置は罰則の対象になることもあります。
歩道橋や道路に横断幕を設置する際に関わる法律はいくつかあります。特に関係が深いのが「道路法」と「屋外広告物法」です。道路上での安全確保という観点からは「道路交通法」も関連しており、交通の妨げとなる掲出はこの法律にも抵触する場合があります。ここで登場する主な法律や用語を整理しておきましょう。
| 法律名 | 概要 | 目的 |
|---|---|---|
| 道路法 | 道路の安全で円滑な通行を確保するための法律。道路上に物を設置する場合には「道路占用許可」が必要で、歩道橋・ガードレール・街路樹などの使用を無断で行うことは禁止されています。 | 道路を公共の空間として安全に利用できるようにするため。 |
| 道路交通法 | 車両や歩行者などの交通安全を守るための法律。運転者の視界を妨げるような位置や内容の横断幕は違反とみなされることがあります。 | 通行の安全・秩序を保つため。 |
| 屋外広告物法 | 屋外に設置される広告・看板・横断幕などを規制する法律。実際の運用は各自治体の「屋外広告物条例」によって細かく定められています。 | 景観・防災・安全を保護するため。 |
それぞれの法律で必要となる主な許可
- 道路法:「道路占用許可」が必要です。歩道橋や道路上の構造物を使用する場合、所管の道路管理者(市区町村・都道府県・国交省など)へ申請します。無許可で設置した場合は、撤去命令や罰金の対象となることもあります。
- 道路交通法:交通の安全を妨げる設置は「公安委員会(警察)への申請」が必要となる場合があります。特に、信号機や標識の近く、視界を遮るような掲出位置は注意が必要です。
- 屋外広告物法・条例:「屋外広告物許可」または「届出」が必要です。横断幕は広告物として扱われるため、掲出場所・サイズ・期間などに制限があり、自治体によって基準が異なります。
それぞれの法律で求められる主な許可を、以下の表にまとめました。
| 法律名 | 必要な許可 | 申請先・ポイント |
|---|---|---|
| 道路法 | 道路占用許可 | 歩道橋やガードレールなど、道路上の構造物を使用する際に必要。 市区町村・都道府県・国交省など道路管理者へ申請。 |
| 道路交通法 | 公安委員会(警察)への申請 | 信号機や標識近くなど、交通の妨げとなる位置への設置時に必要。 安全確保のため警察署で確認。 |
| 屋外広告物法・条例 | 屋外広告物許可・届出 | 横断幕・看板・のぼりなどが対象。 掲出期間・サイズにより自治体への許可や届け出が必要。 |
横断幕以外にも許可が必要な掲出物
横断幕以外にも、屋外で目にする多くの広告物がこれらの法律・条例の対象になります。特に、以下のようなものは設置前に許可や届け出が必要な場合があります。
- 看板:建物の壁面や屋上に設置する広告物。サイズや高さ、照明の有無によっては屋外広告物許可が必要です。
- のぼり旗:店舗前などに立てる旗型の広告物。地面に固定する場合や歩道にはみ出す場合は、道路占用許可が求められることがあります。
- 懸垂幕・垂れ幕:建物の壁面や窓から垂らすタイプの幕。掲出期間やサイズの制限が設けられている自治体が多いです。
- 立て看板・スタンドサイン:歩道に面して設置する場合、通行の妨げになると道路法や交通法に抵触する場合があります。
このように、横断幕だけでなく、屋外広告全般が法令や条例によって管理されています。安全性や景観を守るためにも、掲出前には必ず管轄自治体や警察への確認を行いましょう。
設置場所ごとのルールと注意点
横断幕を掲出できる場所はさまざまですが、設置場所によって申請先や条件が異なります。代表的な設置場所と注意点を紹介します。
① 歩道橋に掲出する場合
歩道橋はほとんどが自治体または都道府県の管理物です。掲出する際は道路管理課への許可申請が必要で、公共目的(啓発・安全運動など)以外は許可されにくい傾向があります。素材は防炎ターポリンなどの安全基準を満たしたものを使用し、風による落下防止のための複数箇所固定が求められる場合があります。
② 道路沿いフェンス・ガードレールに掲出する場合
道路の種類(国道・県道・市道)によって管理者が異なります。国道は国土交通省、県道は県、市道は市町村の担当部署です。許可なく設置すると撤去命令の対象になることもあるため、掲出前に必ず管理者へ確認しましょう。また、信号機や標識に近い位置はドライバーの注意を妨げるため、設置が制限される場合があります。
③ 学校や教育施設に掲出する場合
学校のフェンスや校門前などは、学校または教育委員会の許可を得れば掲出可能です。行事告知・部活動応援などの掲出が多く、比較的自由度が高いですが、近隣道路への影響がある場合は別途申請が必要となることもあります。
④ 公園・公共施設に掲出する場合
市民公園や体育館、コミュニティセンターなどに掲出する場合は、施設管理者(市町村の公園緑地課など)に申請します。安全上の理由から、高さ制限や掲出期間が設定されていることが一般的です。
⑤ 商業施設・企業敷地に掲出する場合
ショッピングモールや会社の駐車場フェンスなど、私有地内であれば自由に掲出可能です。ただし、道路から見える位置にある場合は屋外広告物条例の適用を受ける可能性があるため、自治体の窓口で確認しましょう。
⑥ イベント会場や仮設スペースに掲出する場合
イベント用スペースや仮設フェンスでは、主催者・管理者の許可で掲出できます。風が強い場所では安全性を重視し、メッシュターポリンなどの通風性の高い素材を選ぶのがポイントです。
以上をまとめると、設置場所別の違いは以下のようになります。ここで紹介した素材(防炎ターポリン、メッシュターポリン、トロマット、スエード)については、後ほど詳しくご紹介します。
| 設置場所 | 申請先・許可 | 主な注意点 | おすすめ素材 |
|---|---|---|---|
| 歩道橋 | 自治体・道路管理課 | 防炎素材必須/期間制限あり | 防炎ターポリン |
| 道路沿いフェンス | 国・県・市の道路管理者 | 視界妨害に注意/無断設置NG | メッシュターポリン |
| 学校・教育施設 | 学校・教育委員会 | 近隣への配慮/期間設定あり | スエード・トロマット |
| 公園・公共施設 | 市町村(公園緑地課など) | 安全対策必須/高さ制限あり | 防炎ターポリン |
| 商業施設・企業敷地 | 所有者(私有地) | 道路面から見える場合は条例適用の可能性 | メッシュターポリン |
申請の流れと確認すべきポイント
歩道橋や道路沿いに横断幕を掲出する場合は、掲出場所の管理者を確認し、事前に申請を行うことが基本です。無許可で設置すると撤去命令や罰則の対象になることもあるため、以下の流れを参考に準備を進めましょう。
- 管理者を特定する:
歩道橋 → 市区町村・県の道路管理課/国道 → 国土交通省・地方整備局/私有地 → 所有者。
どの区分に該当するかをまず確認します。 - 申請窓口へ相談:
管理者の窓口に「横断幕を掲出したい」と伝え、必要書類や条件を確認します。
自治体によっては掲出目的(地域行事・安全啓発など)に制限がある場合があります。 - 必要書類を提出:
設置位置の図面、掲出期間、サイズ、素材、防炎証明書などの提出を求められます。
写真で完成イメージを添付すると審査がスムーズです。 - 許可書の交付:
内容に問題がなければ、数日〜1週間程度で許可が下ります。
掲出中は許可書の写しを現場に携行し、期限を超えないよう注意します。
なお、許可期間が過ぎたまま掲出を続けると違反扱いになることもあります。期間満了後に再利用する場合は、再申請を行うようにしましょう。
安全性を考慮した素材選び
歩道橋や道路沿いに掲出する横断幕では、風・雨・紫外線といった屋外環境への耐久性が重要です。素材によって耐久性・重量・視認性が異なるため、設置場所や使用期間に合わせて選びましょう。
ターポリン
ポリエステル布に塩化ビニール(PVC)をコーティングしたシート素材で、屋外幕の定番素材です。防水性・発色性・強度に優れ、長期掲出にも対応できます。防炎認定を取得した製品を選べば、学校や公共施設などでも安心して使用可能です。また、光を通さない遮光ターポリンもあり、裏写りを防ぎたい両面デザインや、屋内展示にも適しています。
ターポリンについて詳しくは以下の記事もご覧ください。
>>ターポリンとは?生地の特徴や用途を紹介
>>ターポリンのメリット・デメリットを徹底解説!
メッシュターポリン
風の抜ける細かな穴が空いた素材で、強風対策に最適です。通風性が高いため、フェンスや歩道橋など高所での掲出でも安全性を確保できます。軽量で取り扱いやすく、短期イベントや季節ごとの掲出にもおすすめです。透け感があるため、デザイン時には背景色とのコントラストを意識しましょう。また、光の透過を抑える仕様の遮光メッシュターポリンもあり、強い日差しの下でもデザインをはっきり見せたい場合に適しています。
メッシュターポリンについて詳しくは以下の記事もご覧ください。
>>メッシュターポリンは文字がきちんと見える?
トロマット
ポリエステル系の布生地で、軽くてシワになりにくく、屋内外問わず使いやすい素材です。柔らかな質感で光沢を抑えた仕上がりのため、イベント会場や学校フェンスなど「やさしい印象」を与えたい場所に適しています。ただし、完全防水ではないため、雨天が続く場所ではターポリン素材がより安心です。
トロマットについて詳しくは以下の記事もご覧ください。
>>幕に使用される「トロマット」生地とは?
>>どっちを選べばいい?ターポリンとトロマットそれぞれの特徴などを解説!
スエード
表面に微細な起毛を持つポリエステル素材で、上品で落ち着いた印象を与えます。厚みがあり光を通しにくいため、屋内外のどちらでも使用可能です。展示会や式典、学校行事の横断幕など、デザイン性を重視した掲出におすすめです。また、光を完全に遮る遮光スエードもあり、照明環境が変化する室内や屋外イベントでも安定した見え方を保ちます。ただし、重量があるため高所掲出には不向きです。
スエードについて詳しくは以下の記事もご覧ください。
>>幕に使用される「スエード」「遮光スエード」生地とは?
素材を選ぶ際は、掲出期間・設置環境・風の強さなどを総合的に考慮することが大切です。風が強い地域ではメッシュターポリン、長期掲出には防炎ターポリン、短期屋内ではトロマットなど、目的に応じた選定が安全性と美観の両立につながります。
当サイトで取り扱っている各素材については、こちらのページでも詳しくご紹介しています。
▶ 取り扱い生地のご紹介
デザイン・サイズ・掲出期間のポイント
歩道橋や道路沿いの横断幕は、通行人やドライバーなど「動きながら見る人」が多いため、遠くからでも一目で伝わるデザインを意識しましょう。また、掲出期間によっては素材劣化や色あせにも注意が必要です。
- 文字は短く・大きく:見出しのように短く、印象的なフレーズを使用。
- 背景と文字のコントラスト:白地×黒文字、黄色地×赤文字など、視認性の高い組み合わせを意識。
- ロゴ・QRコードの配置:デザイン中央や左右に余白を確保し、判読しやすく配置。
また、掲出期間の制限にも注意が必要です。多くの自治体では「1週間~2週間以内」などの期間制限を設けており、延長掲出の場合は再申請が必要となるケースもあります。許可申請時には掲出場所と期間を正確に記載し、管理者とのトラブルを避けましょう。
歩道橋|横断幕の製作事例
こちらは、合同会社Delightful様よりご依頼いただいた、交通規制告知用の歩道橋掲示幕の製作事例です。車両からの視認性を重視し、遠くからでもはっきりと読める赤文字デザインで仕上げました。
素材は遮光ターポリンを採用し、太陽光の影響を受けにくく、昼夜問わず高い視認性を確保しています。また、風の影響を考慮し、風穴加工を2箇所に施して安全性を高めています。周囲ロープ縫い込みによる強度補強と、ハトメによるしっかりとした固定で、風圧の強い歩道橋でも安心して掲出できる仕様です。
まとめ
歩道橋や道路沿いに横断幕を掲出する際は、まず道路法・道路交通法・屋外広告物法(条例)といった関連法令を理解することが第一歩です。公共空間では必ず許可申請が必要であり、無断で設置すると撤去や罰則の対象になる場合もあります。掲出を検討する際は、「誰が管理している場所か」を確認し、自治体や警察への相談を欠かさないようにしましょう。
また、設置場所や目的に応じて素材を選ぶことも重要です。ターポリンは屋外用の定番、メッシュターポリンは風の強い場所に最適、トロマットやスエードは学校やイベント会場などに向いています。遮光タイプを選べば日差しの影響を抑えられ、視認性を維持しながら安全に掲出できます。
さらに、デザインの視認性も大切なポイントです。「短く、はっきり、大きく」を意識し、色のコントラストや配置バランスを工夫することで、通行者やドライバーに伝わる横断幕を制作できます。
法令を守り、安全に配慮しながら掲出すれば、地域のイベントや啓発活動を効果的に発信できます。当サイトでは、掲出場所・目的・素材に合わせた最適な仕様をご提案しています。制作前のご相談やお見積もりも承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▶ お問合せはこちら